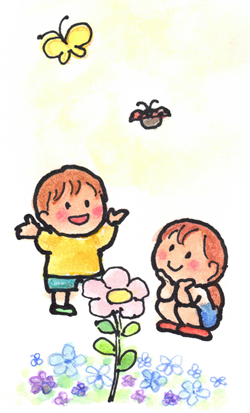保活ってどうすれば? 私の2回の体験記 ②見学編
2023年09月16日(土) 10時00分
こんにちは。すくナビ編集委員のけろっぴです。保活ってどうすれば?私の体験記、2回目は見学編です。
赤ちゃんを抱えながらの見学は大変です。だからといって見学をせずに保育園を選ぶのは怖い。ですが、見学に行っても、何を見ていいのか、何を聞いていいのか、よくわからない。そういう親御さんも多いのではないでしょうか。
ここでは、私の2018年と2022年の2回の保活経験をもとに
・見学の手順
・見学でみたポイント
について振り返ろうと思います。
見学の手順
はじめにするのは、園に電話をして、見学の申し込みをします。入園を検討していて見学をお願いしたい、と伝えれば、たいてい見学可能な日を教えてくれます。電話は10時から11時、13時から14時など、保育園が比較的落ち着いている時間帯にしました。
電話した時には、当日何を持って行けば良いかも聞きました。靴を入れるビニール袋を持ってきてください、筆記用具を持ってきてください、など要望を伝えてくる園もあります。
また、ベビーカーで見学に行っていたので、ベビーカーをどこに置けば良いかも一緒に聞きました。おかげで、見学当日に焦らないですみました。
見学でみたポイント
さて、見学です。たいてい見学は平日の保育時間中(午前10時や午後3時)に指定されることが多かったです。0歳児をつれての見学は、なかなか大変で、自宅を出ようとしたときにうんちをしたり、気持ちよく眠ってしまったり。冷や汗をかきながら、保育園の送迎ルートを確認しつつ、向かいました。
見学ではたいてい主任クラスのベテランとみられる保育士が案内してくれました。保育室の見学、調理室や給食の説明、1日の過ごし方、お散歩に行く公園の案内、室内での遊び方、園が力を入れているポイント(体育や英語などのアクティビティ、食育活動)などを説明してくれます。
私が見学で見たポイントは以下のようなところです。
① 安全安心
「SIDS(シズ=乳幼児突然死症候群)対策は何をしていますか」という質問は必ずしていました。どう答えるかはもちろんですが、きちんとすぐに答えられるかどうかを、安全安心についてきちんと取り組んでいるかを判断する基準にしていました。
保育士の配置が、国の基準を満たしているかもチェックしました。1人の保育士がみてよい子どもの数は、0歳児は3人、1歳から2歳児は6人、3歳児は20人、4歳から5歳児は30人と定められています。この基準を頭に入れて、保育士の数がぎりぎりか、多めに配置されているか、といったことをチェックしていました。
② 保育時間の確認
「延長保育はいつから使えるか?」も、必ず聞いていました。1歳になったら使える、1歳児クラスにならないと使えないなど、園によってさまざまだからです。
私は妊娠前、仕事の帰宅が午後9時になるのが普通だったので、延長保育ができるかどうかは重要なポイントでした。
ですが、保育園のパンフレットなどで閉園時間が午後10時となっていても、実際に午後10時まで預けている人はいないということを1回目の保活で知りました。保育園に通い出して感じるのは、延長保育を使っている家庭でも、お迎えは遅くても午後7時半ごろ。育休から復帰した後は、働き方を根本的に変えなければと感じた瞬間でした。
また、兄弟姉妹を計画しているひとは、育休中の受け入れについて聞くのもいいかもしれません。目黒区は育休退園はなく、下の子が満1歳になる年の翌年の4月末まで、上の子の保育園は継続して利用できます。ですが、「育休中のお迎えは●時までに」とお願いする園もあるようです。第1子が通った園はそうしたお願いはありませんでしたが、友人が通った園はあったと聞きました。
③ 保育環境
「散歩によくいく公園」「園庭の有無」「(園庭がない場合)ヒーローバスを使う頻度」「水遊びはどうしているか?」「どんな行事があるか?」などをチェックしました。体育祭や夏祭りをやっている保育園も多いので、どんなことをやるかを聞くと、保育園の雰囲気を知るきっかけになりました。
「保育士の離職率」を聞いている親御さんもいました。保育園に通うと、保育士の入れ替わりがけっこう多いなと感じます。離職率が低いほうが職員にとっても良い園なのかなと判断する材料になるのかなと思いました。
ほかにも「体育や英語などアクティビティの有無」「写真の販売の有無」などもチェックポイントだと思います。アクティビティが有料な場合は月謝のチェックも忘れずに。
利用する保護者向けに、保育中の写真のほか、動画を見られるようにしている園もあります。
④ 保護者の負担
「保護者が毎日用意するもの」「保護者参加の行事は」「保護者会はあるか」「朝やお迎え時の受け渡し方法」「送迎用の自転車置き場、ベビーカー置き場、だっこひも置き場はあるか?」「おむつなどのサブスクはあるか」「連絡帳はアプリか手書きか」といったことも確認しました。「使用済みおむつ」は園が廃棄してくれるところがほとんどで、たいてい説明がありますが、話がでなければ聞いた方がいいと思います。2018年に見学した時は1園、保護者持ち帰りのところがありました。
これらの情報は、目黒区のホームページにもまとめてあります。一覧で見られると、ありがたいですね。
→https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/kosodate/hoiku/ninka/ninnkahoikuenngaiyou.html
⑤ 園内の雰囲気
いろいろと書いてきましたが、見学で最も大事なポイントは、「我が子を通わせたい!」と思えるかどうか、だと思います。
子どもたちは楽しそうか、保育士がいきいきしているか、園内の雰囲気は自由そうか、規律正しそうか、園長の雰囲気が良いか、あと園内の掲示物(子どもたちの制作や園だより)なども眺めて、うちの子どもも通わせたいな、通わせてもいいな、と思ったら見学の目的は達成でしょう。
私は2018年のときは20園ほど、2022年のときは4園、見学しました。
正直、見学だけで良い保育園、悪い保育園を見極めるのは難しい。ですが、違和感を感じることはできます。
というのも、2018年にある保育園を見学した時に、土曜のお昼寝の時間を指定してきた園がありました。多くの園は平日日中の保育の様子を見ることが多かったので「ん?」と思いました。後に聞いたところ、保育士の大量退職があり、園の運営にも問題があったようです。見学に行かなければこの違和感に気づけませんでした。
あとは児童館などに行って、雑談ついでに保育園に通わせている保護者がいれば評判を聞くのが、一番リアルだと思います。児童館や子どもたちの集まりでは、よく保育園の話になります。みなさん快く答えてくれると思います。
話しかけるほどの勇気がない…という方は、福ナビというサイトで、第三者評価の結果を検索するのもいいと思います。
→https://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/hyoka/hyokatop.htm
以上で見学編は終了です。
さて、次回3回目では保育園の優先順位付け、申し込み方法、第一希望に入れるには(加点を得るには…)について、お伝えしようと思っています。
(編集員:けろっぴ)